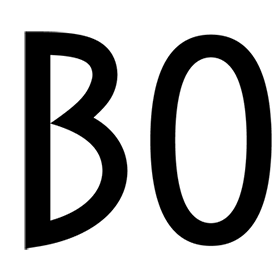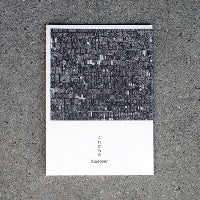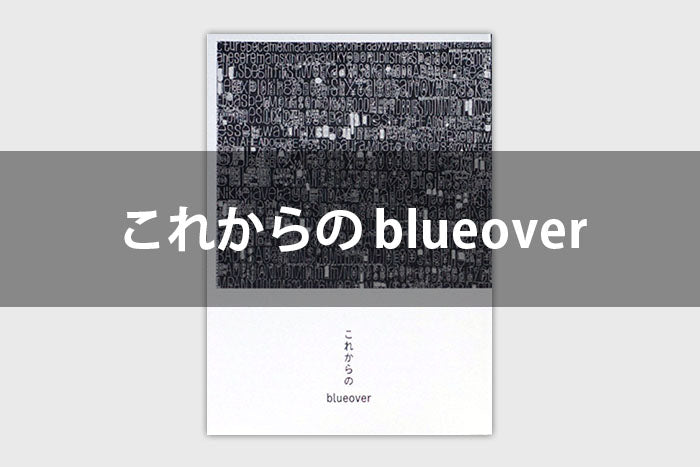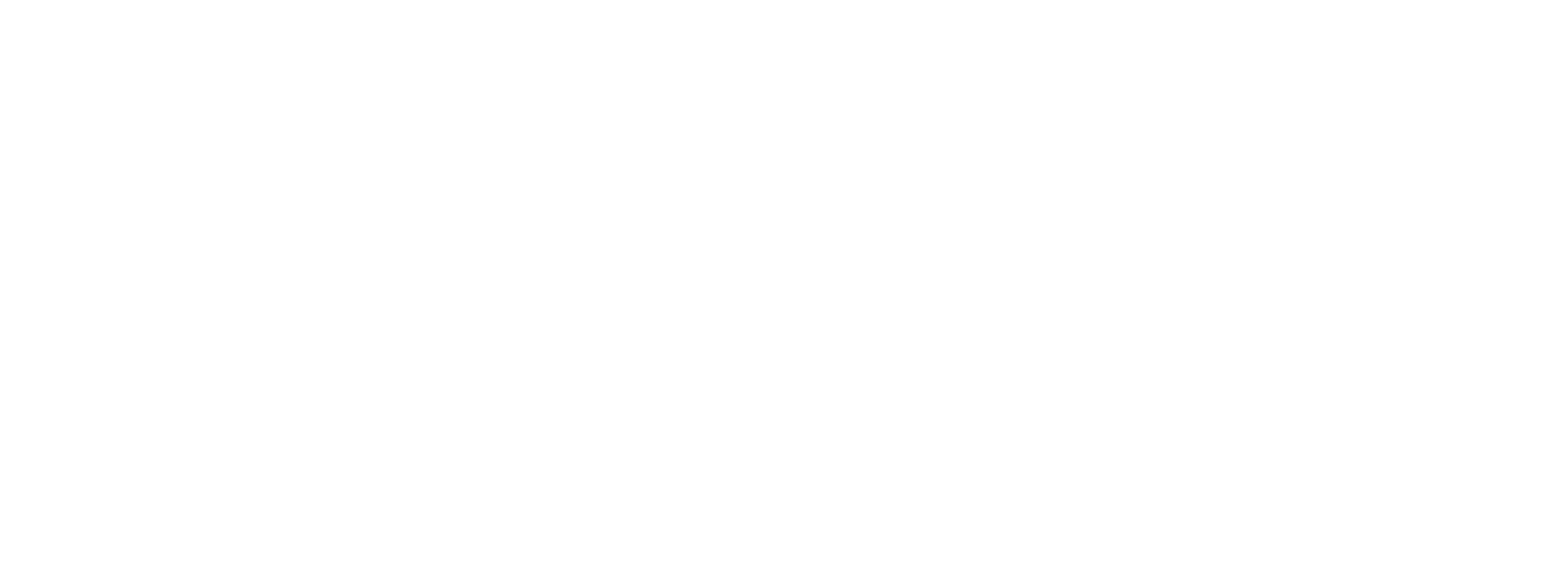コンセプト深堀インタビュー
ブルーオーバーがコンセプトを刷新。その理由と意味を掘り下げる…
デザインや機能を気に入ったから、物を買う。それがわたし達の普通でした。だけど、その普通が今変わりつつあります。例えば、いくら便利でも、オシャレでも、必要以上に大量生産して、余らせた物を漫然と捨てていたら? 物自体のデザインや機能を気に入っても、ブランドのバックボーンやビジョンが肌に合わなかったら、買わない。それがわたし達の次の普通になっていく。そんな気配がします。
だからというだけではありませんが、設立10年を迎え、ブルーオーバーはコンセプト文を新しくしました。理念はそのままに、より詳しく説明したという方が適しているかもしれない、新コンセプト文。そこには、ブランドの背景や物作りの考え方、そして履く人と共有したい思いを込めています。
【コンセプト全文】
このコンセプト文、なんと2500文字以上あります。タイトルにもありますが、コンセプトにしては長すぎる!というほどの長文ですが、実はできる限り簡潔まとめてこの字数。そんなところからも既に、この文章に込めた思いの丈が伝わるかと思います。一方、簡単にまとめるために触れられなかった部分も多くあります。
なのでこのコンテンツでは、コンセプト文を少しずつ参照しながら、ブランドコンセプト文を執筆したデザイナー渡利にスタッフ江川が質問して、内容を掘り下げていきます。
人物紹介
渡利(ワタリ)
ブルーオーバーの発起人であり、デザイナー。たまの趣味は木彫り。愛車は初代ホンダシティE-AA。
江川(エガワ)
ブルーオーバー / ストラクトのスタッフ。休日は手芸を楽しむ。作った物をすぐ使えると嬉しい。
江川
ブルーオーバーのコンセプト文、書いて、編集してを繰り返してようやく完成しましたが、どうにか読みやすい長さの文章に整えるために、端折ってしまった部分も多いですよね。その部分もまるっと伝わるように、文章の意図しているところを要所要所、執筆者である渡利さんに質問していきたいと思います
渡利
はいー!よろしくおねがいします
江川
では、早速コンセプト文の原文を参照していきましょう
はじまり
ブルーオーバーは大阪で生まれたスニーカーブランドです。私(渡利ヒトシ)はフリーランスとしてプロダクトデザインの仕事を請負う中で、製品開発、消費のサイクルに疑問を持ちはじめていました。
江川
早速質問なのですが、プロダクトデザインという言葉を直訳すると「製品のデザイン」ですよね。具体的には、どんな物をデザインしていたんですか?
渡利
よく手掛けていたのはスポーツ用品や家電製品ですね。当時はUIUXといった言葉は少なく、いわゆるハードウェアと言われる製品の外装を主にデザインしていました
江川
スポーツ用品と家電、実はどちらもプロダクトデザインの広い領域の中にあります。一聴すると同じデザイナーが手がけるにしては分野が離れていて意外な感じもしますよね。…こっちの方向に話しを広げると脱線するので本題に戻るとして。
そういった製品を手掛ける中で消費のサイクルに疑問を持ったと
渡利
やっぱり、商品を購入してもらうために、企業は毎年刺激的なモノをうみださなければならない。その理屈は十分に理解できるし、ある側面ではそうあるべきだと思うんですけど、そのサイクルだとモノをうみだす行為が瞬間的な消費をうながしてしまうんです。そうなると、表面的な化粧としてのデザインが繰り返される状態になりやすく、本当の価値を持ったモノが生まれにくいし、理解されにくい土壌になっていくなぁと思ったんです

江川
なるほど。確かにわたしも、「物」自体が古くなったわけでもないのに、中身はそう変わらない新しいものがどんどん出てきて、相対的に以前つくられた物を古く感じる。そのサイクルが常態化していることに疑問を感じてしまいますね…
…さらに、国内の製造工場の衰退を目の当たりにし、2011年に自らの身をそのサイクルに投じることで変化を起こすことは出来ないかと、ブルーオーバーを立ち上げました。
江川
2011年にブルーオーバーを立ち上げた、というのは何か契機になる出来事があったのでしょうか?
渡利
2000年代当時、不景気のあおりを受け、マーケットのコスト競争が厳しくなる中、多くの靴メーカーはアジアにシフトしていきました。それが更なるコスト競争を呼び起こし、より消費的なサイクルを加速させて、国内に残った小規模の工場はますます厳しい状況に追いやられる傾向になった。最終的に、これまで国内で作り続けていた小さな工場の撤退や廃業が増えることになります。それを目にしたのが一つのきっかけですね
江川
ブルーオーバーを立ち上げる以前から、そういった小規模な靴工場との繋がりがあったんですね。さっき言っていたスポーツ用品を作る工場がそれにあたるのでしょうか?
渡利
そうですね。大小さまざまな工場に出入りはしていました。そこで直接職人さんと話をしたり、工場の社長さんとも話をしました。あと現場の空気感なんかでも、前述のような状況を感じることができました。そんな生産の背景を目の当たりにしたこと、そして自身がフリーランスという立場としてやれること、できることは何か。そんなことを考えてると、自らが地場産地に対してアクションが起こせないかという考えが生まれたんです。その結果がブルーオーバーだったというわけ
江川
そうやって誕生したブルーオーバーだからこそ、10年間ずっと日本製にこだわってきているんですね。
さて、次は章をうつってブルーオーバーの靴作りの背景についての部分を読み進めます
靴作りの背景
靴という製品は、アッパー、底材、紐、中敷といった多くの資材で構成されており、そのどれもが小規模なマニュファクチュアでの分業体制をとった製造工程をたどります。…
江川
これってつまり、平たく言うと…
渡利
アッパー、底材、紐、中敷、全部違う場所で作っているってことですね
江川
作っている「場所」が違うというのも勿論ありますが、一つの大きな会社が色々な場所に工場を持っている、ということではなくて、それぞれ運営している人や会社自体が異なるってことですよね?
渡利
そうです。更にアッパーで言うと、材料であるレザーを売っている会社、そしてその材料をアッパーの形に加工する会社も違います
江川
それが更に、ソールならソール材を売っている会社、加工している会社、とそれぞれに派生していく。コンセプト本文に書いてあるよりも、本当に沢山分業されているのが靴作り。
靴って本当に手間暇がかかってるな~…
あとつぎ問題や高齢化、海外でのコスト競争などさまざまな理由から、完全に日本国内のみでスニーカーを生産することは困難となってきていますが、ブルーオーバーはできる限りの資材を国内で調達し、製造を行っています。決して大きな規模感ではありませんが、工場同士の繋がりや地域の結びつきを活かしながら、国内の製造現場を失わないようにしていきたいと考えています。…
江川
中々、コンセプト文の中では触れにくかったところだと思うのですが、完全に日本国内でのみスニーカーを生産することは困難となってきている、というのはどういったことが理由にあるんでしょう?
渡利
困難の理由は、端的に言うと「国内で靴を作って売ってもお金にならない。だから業者が増えずに消えていくほうが多い」ということだと考えてます
江川
更につっこむと、何故お金にならないのでしょうか?
渡利
さっきも話に出ましたが、靴は皆さんが思っている以上に多くの人の手で作られています。つまり部材が出来上がるにはそれを加工する手間や技術に対して工賃(人件費)もかかるということ。工賃は国や地域で異なるので、日本とアジアを比べると当然アジアの方が安いです。結果、国内で靴をつくると、海外で作るより相当高いものになってしまうんです

江川
なるほど、ざっくりいうと人件費が原因で価格競争に勝てないということか…
渡利
そうすると、国内工場に依頼するブランドは少なくなり、売り上げが立たないので国内で靴を作る場所は増えることはなく、減っていくことになります
江川
それは分かるのですが…古くから日本に大きい靴工場を持っているメーカーは除いても、日本製の靴はブルーオーバーだけでなくちらほら目にしますよね。しかも、ブルーオーバーより安価なことがもっぱらです
渡利
そうやね。靴はノックダウンという、アッパーとソールそれぞれ半製品の状態で輸入して、国内でアッセンブリして靴に仕上げる手法があります。それを行う製靴工場(靴を作り上げる最終工程)は比較的規模が大きいので国内にもまだ存在しているんです
江川
その製法でも、メイドインジャパンはメイドインジャパン、なんですね
渡利
そうです。これの意味するのは靴としての品質の保証が最終工程の「製靴」にあり、日本のメーカー(工場)が最終工程を担うことで、その品質を担保しているという証にもみれます。僕たちの商品はアッパーもソールも国内で作っていますが、お客様から見れば同じメイドインジャパンとなります
江川
なるほど。そんな中で、ブルーオーバーは可能な限り全工程を日本国内で生産することにこだわっている
渡利
正直すべてを国内で作りあげる意味はどこにあるのかを考えなければならないと思っています。98%が輸入になっているアパレルを見ても、時代の流れは変えることは出来きないでしょう。その上で僕たちがすべきアクションがなんなのかを考えることが大事です
江川
やはりその、次のアクションを考える時、ブランドスタート時の地場産業に対する思いというのが大きく占めてくるのでしょうか
渡利
僕はノックダウンも一つの選択肢としてはアリだと考えています。ただ、少なくなっているとはいえ、国内に裁断、縫製場、革漉き、インソール、副資材問屋などのこまかなことをされている方たち、職人さんがいる限り、できるだけ国内製造にこだわっていきたいですね。先人たちが過去からつないできた文化的財産を、残せるなら残していきたいです。その活動こそがブランドの意味とも考えているので
江川
ブランド内で渡利さんや靴職人の東さんが材料調達や工場との調整に手間暇をかけているのを見ると、「ブルーオーバーのように靴作りのほぼ全工程を国内で行うことは、ちょっとやそっとじゃ真似できないだろうな。だからブルーオーバーは唯一無二のブランドだな」と思う反面、もっと盛り上げないと工場が少しずつ衰退していくのを止められないんじゃないか…と不安になるのも正直なところですが…。
話しを少し戻して、原文の続きを見ていきましょう
…それはなぜか。
私は1980年代後半から2000年まで、まさに日本がモノヅクリ大国と呼ばれていた時代に生まれ育ち、自らも製品のデザインという仕事に携わり様々な工場に足を運んできました、そんなこれまでの日本を支えてくれた製造業に対して恩返しをしようと考えているからです。
江川
さっきの話しと少し重複しますが、何故ブルーオーバーが可能な限りの工程を日本で行っているかを説明している部分ですね。この辺りを読むとブルーオーバーは「靴だけ」を作っているのではなくて、正に「取り組み」とか「チャレンジ」って言葉が似合うな、と感じます
渡利
やっぱり子供のときの原体験って、自身のアイデンティティにもなっているなぁとも思うんです。そういった意味でいうと、80年代~00年はモノの時代だったわけです。あの頃はモノに囲まれて、ワクワクさせてもらって、刺激をうけて育ちました。前職がプロダクトデザインを目指したのもそういった時代背景に影響されていた結果だろうね
江川
わたしは90年代生まれなので、そんな時代の残り香を微かに感じた覚えはあります笑

渡利
モノづくりの現場(工場)は立ち入ったときの機械のにおいや、風景もすごい好きで刺激を受けます。恩返しと書くと大層に聞こえますが、ただ純粋に身近にモノヅクリの場所を失いたくないと考えている。ただそれだけだと思っています。失わないために、何ができるのか。そういった意味ではブルーオーバーは靴だけでなく、取り組みやチャレンジといった言葉も兼ね備えているとは思うね
江川
そうですね。わたしもブランドの一員として、果敢にチャレンジし続けたいです
民藝運動からの影響
私は仕事(プロダクトデザイン)を行うなかで、一つの運動に影響をうけています。それは柳宗悦氏の提唱する民藝運動です。
江川
柳宗悦氏というと、プロダクトデザインの巨匠、柳宗理氏のお父さんですよね。 柳宗理さんは渡利さんやわたしのような、デザインを学ぶ人、学んだ人は必ず通る著名なデザイナー。名前は聞いたことなくても、カトラリーやキッチンツールなんかを見たことある方は多いかと思います
渡利
そうです。実は民藝を知るきっかけは、宗理氏が手掛けたプロダクトだったんです
江川
そうなんですね。そこからどうして宗悦さんの民藝の方に興味が向いたんですか?
渡利
デザインに興味を持った当時、さまざまな工業製品のなかに、一際魅力的に映ったのが宗理氏のプロダクトデザイン群でした。意匠に無駄がなく、合理的でありながら、それでいて温かみある道具。当時はそのフォルムにただ単純に惹かれました。ほかの均一的な工業製品とは違って、人が見えた感覚を覚えています
江川
人が見える、というと?
渡利
多分、哲学者の鞍田崇さんがいわれているインティマシー(いとおしさ)のようなものを感じたのかなぁ。そこから何故そういう「いとおしさ」を感じる形や雰囲気になるのか。それを見つけようと掘り下げていったことで、父である宗悦氏の「民藝」にたどりつくことになりました
江川
渡利さんは、同じプロダクトデザイナーである宗理氏に興味を持ったことをきっかけに、父であり哲学者の宗悦氏を知って、影響を受たんですね。わたしも学生の頃、民藝について学んだとは言え概要部分だけだったので、ブルーオーバーのスタッフになってから改めて、宗悦氏の著書をあたって詳細を知りました。日本民藝協会のホームページを見ると、民藝の特性についてこんなことが書かれてますね
実用性。鑑賞するためにつくられたものではなく、なんらかの実用性を供えたものである。
無銘性。特別な作家ではなく、無名の職人によってつくられたものである。
複数性。民衆の要求に応えるために、数多くつくられたものである。
廉価性。誰もが買い求められる程に値段が安いものである。
労働性。くり返しの激しい労働によって得られる熟練した技術をともなうものである。
地方性。それぞれの地域の暮らしに根ざした独自の色や形など、地方色が豊かである。
分業性。数を多くつくるため、複数の人間による共同作業が必要である。
伝統性。伝統という先人たちの技や知識の積み重ねによって守られている。
他力性。個人の力というより、風土や自然の恵み、そして伝統の力など、目に見えない大きな力によって支えられているものである。
日本民藝協会ホームページより抜粋
江川
ブルーオーバーの物作りにも、共通する部分がいくつかあるような…
渡利
ブルーオーバーを立ち上げる時には、民藝を意識して動いていたつもりはなかったんだけど、改めてこの特性を見たときに通ずる部分があるなって思いました

1900年代前半、工業化による大量生産が始まった時代でした。そして同時に、工芸品は華美で装飾的な存在となり、柳宗悦氏はその背景から、各地の風土や適した環境下のもと、そこに根付いた生活の中に本当の美があるとし、そこで働く名もなき職人たちの手仕事から生まれるモノこそが、衒(てら)いのない用に即した「健全な美」であると示しました。
江川
ここでは宗悦氏の見出した民藝に宿る「美」について言及しています
渡利
一般的には、これまでの道具における「美」の価値基準は、高価な材量をつかったり、有名な工人の手がけたものが美しいとされていたんです。だけど宗悦氏はそうした物質的なものだけではない部分にも「美」が宿ることを見極めたんですね
江川
「美」は一般的には視覚的に美しいを指すものと思いますが、民藝の定義の中では形状について、「ここがこうだから綺麗だ」という風には書いない。つまり、「姿、形」に対しての美しさの話ではないと伝わるんですが、正直さっと読んだだけではわからないというか
渡利
たしかにわかりにくよね。言うように、ここで示している「美」は姿、形だけを指しているわけではないと思います。宗教哲学者でもあった宗悦氏は、宗教的観点からの美のとらえかたを示していると解釈しています
江川
私は民藝に対しては、宗悦氏が言った「用の美」、つまり用途や機能が美につながると解釈していました。用の美(機能美)が民藝がほぼイコールというような
渡利
確かに、そういった受け取り方は多いよね。僕も初めはそういう風に見えていた節があったんだけど、デザインはロジックとしてその道具の成り立ちを紐解き、形に結び付けようとするクセみたいなものがあるからだと思ってます。でも民藝をみていくと決して機能美だけじゃないってことがわかったです
江川
ふむふむ
渡利
そもそもオリジナル?の民藝である美の選定は彼の卓越した審美眼にあって、世間の言う民藝とはまた別のものであると個人的には考えています。昔(1960年-ごろ)民藝ブームがあって、その中で定義をそれぞれ拡大解釈してしまって、今となってはなんだかカオスのような状況にあると思っています。民藝館にある宗悦氏の選定した民藝品はすごいモダンで直感的に美しいとも思えるけど、どこか地方にあるお店で売っている、なんだかなーって思う品も民藝品とうたってたりする
江川
たしかに、民藝という言葉はかなり広義になってきている感じはしますね。…ここでずばり聞くと、ブルーオーバーは民藝なんですか?
渡利
ここまで話してなんですが、実はブルーオーバーが民藝だと思ったことは一度もないんですよ(笑) そもそも自らこのブランドは民藝ですっていうのも変なことだしね。ただ、宗悦氏の思想に影響を受けたことは事実だし、そこに書かれている定義はすごく素敵だなと思っています。もしどこかで、ブルーオーバーは民藝だって言われたら、それはすごい嬉しいことだとは思っています

江川
なるほど! たしかにそうですよね、そもそもそれその物を民藝か民藝じゃないかをジャッジするのは我々ではないという…。つまり、宗悦氏の言う民藝の定義には共感するけど、ブルーオーバーは民藝であろうとしているわけではない。
少し「美」の話に戻すと、渡利さんは宗悦氏の思想をどう解釈しているんですか?
渡利
「地域社会に暮らす人々の中から、必要とされて産み出された道具。その道具はその土地の風土を活かしながら、そこに暮らす地域の人たちにとってはその道具をつくる「仕事」としても存在する。そこに有名無名は無くて、ただ人の営みの中に当たり前に存在している。ヒトとモノが関係しあうその循環が、とっても自然であり健康的で美しいよね!」ってことだと僕は解釈してて、それがすごいいいなって思ってるんですよ。「健全な美」の健全って部分がいいなと思ってます。健全でいて美しいことって素敵だなーって思います
江川
民藝に宿る「健全な美」とは、姿形だけではなく、それを取り巻く背景も含めての「美」を指す。という解釈なんですね。わたし自身、民藝に対する見方もちょっと変わってきたようにも思えます。
ブルーオーバーの、素朴で丸みを帯びた見た目と、日本製というところ。あと、民藝というワード。そこだけ拾うとあたかも民藝を標榜していそうですが(笑) 実はそれだけじゃなくて、宗悦氏のいう健全な美の思想に共感したことは大きな要素ではあれど、前回触れたような消費サイクルに対する疑問などなど…これ以降解説しながら触れていく部分も含めて、他にも沢山内包したアウトプットがブルーオーバーというブランドだ、ということなんですね
生活に存在する美。私はこの考えに強く影響をうけ、現代社会においてもその地域に根付く風土、培われた技術を基礎にした設計を施すことが大事であると考え、極力不要なデザインを行わないように心がけています。その健全な美を生み出すことができる職人たち(産地)を絶やさぬことがブルーオーバーの活動でもあります。
江川
極力不要なデザインを行わない…だからブルーオーバーは、大量生産がベースにある他のブランドと違ってマークがないのでしょうか
渡利
マークがない=アンチ大量生産ってわけではないし、不要とも思ってないです。最近はマークが小さく入っているブランドなんかも多いわけで
江川
衣類のブランドでもかなり増えてますよね
渡利
大々的にサイドにマークを配置した意匠が多かったのは、そういった時代だったんだなと思ってます
江川
流行だったものが定着したってことですね
渡利
でも、僕らの靴のサイドに大きなマークがないのは、確かにブランド名が先にくる状態ではなく、アノニマス(匿名)であるべきだという考えはありましたね。それは名もなき職人たちこそが、僕たちのブランドを作り上げているんだという意思表示のようなものかもしれない

江川
それに、無名性の高い姿だからこそ、素材やフォルムが浮き彫りになった見応えのある姿になっている。という側面もありますよね。職人の仕事が活かされているというか
渡利
それはあるかもしれないね。僕はデザインするとき、お願いする工場さんの得意とすること…強みを第一に考えて設計を始めます。こちらのデザインで、工場に不慣れなことをさせてしまうと、結果として不要な要素が溜まっていってしまうことが多い
江川
不要な要素というと…うーん、それは例えば職人さんの作業工程なんかも含まれるんでしょうか
渡利
そうですね。反対に工場が得意な手法をうまく取り入れて設計すると、非常に美しいモノになっていきます。これは素材に関しても同様のことが言えます
江川
つまり無理なことをすると、非効率でかっこ悪いものが生まれてしまうと。ブルーオーバーはなるべく、無理なことはしないように、工場の強味を活かして、素直に、自然に出来上がる形を見届けようということですね。確かにそれは、最終的に姿に表れているように思います
デザイン
次に、ブルーオーバーが施すデザインとは何か。それは、あたりまえをデザインする。つまり、靴としては「快適な履き心地」であるということです。
例えば、日本人の足型に合わた木型を削る。履けば履くほど足に馴染む素材を選ぶ。足を曲げたときにストレスないように型紙を設計する。走る、ではなく、歩くために最適なソールの硬度を設定する。流行に左右されることなく履き続けられる飽きのこない外観。
江川
この部分では、ブルーオーバーがどのようなことを考えて、靴作りをしているかについて触れていますね
渡利
スペシャルな機能ではなく、当たり前の機能。それを満たすことが大事だと考えています。僕らの靴は、「歩く」という最も当たり前の動作に向けて設計しています。だから特別ではなく、当たり前の機能をちゃんとすることを意識してますね
江川
速く走る!とか、跳ぶ!とかではなく、当たり前に歩くこと
渡利
そう。当たり前に。でもね、それってとても難しいなとも思えたりします。例えば、非常に”ふわふわ”した履き心地の靴を履いたとき、はじめ「おおっ!」っと思ってはもらえるけど、その”ふわふわ”、長く履くとかえって疲れるんです
江川
そうですね。この部分、店頭でお客さまに説明すると驚かれることが多いです。わたしも初めて聞いた時は目から鱗でしたけど、これまで履いてきた”ふわふわ”靴をふり返ってみると、たしかに疲れてたかもな~って、妙に納得しました

渡利
“ふわふわ”ってことは、足を支えるソールが安定していないという状態なんだけど、その場合、足の方がその不安定を補おうと常にバランスをとる状態になっていて足が疲れてしまう。でも履き始めはそのスペシャルな”ふわふわ”した機能の方がインパクトがあって、いいなって思われる
江川
極端にいうと、ベッドの上で歩くのが疲れるのと同じ感じですかね。走る時には、衝撃を吸収してくれる”ふわふわ”は必要なんですけどね
渡利
一方ブルーオーバーは、履いてみて「ふんふん普通だな」ってなる。すると、その良さってわからないですよね
江川
むしろ、ランニングシューズと比較したら、最初に「なんだこれ、硬いな」って感じる人が多いかも(笑)
渡利
でもこれは「歩く」と「立つ」という動作において、程よいバランスで設計した「硬さ」なんです。それで、長く履いてみて初めて、「あれ?これいいじゃん」ってなる。良さがわかってもらうまで、結構長い時間が必要なんです
江川
それは、ほんとにそうというか…
渡利
そういったことも含めて、靴ってのは履いてみて、時間がたってその良さがわかるっていうのがなんとも言えない難しさがあるなーって思います。
それで、僕が一番いいなって思うのは、「いつの間にかよく履いているな、この靴」っていう靴になれること。気付いたらレギュラーっていう声が一番うれしいです
江川
何足も持ってます!ってお声も、「良さが伝わったんだ」って、本当に力になりますね
そして次に大切な要素は、「長く使用できること」です。長く使用していただけるように、丈夫な素材を選び、つま先やカカトの芯材もしっかりとしたものにする。モデルによって、削れにくい底材を採用したり、交換できる製法を用いる。それらは当たり前のようではありますが、簡単には実現できないものでもあります。ブルーオーバーが施すデザインとは、快適にいつまでも長く履き続けられる靴をデザインすることなのです。
江川
ブルーオーバーの靴は、資材一つ選ぶにしても一気通貫する理念がある。それはとても耳障りの良い話しですが、価格とのバランスを取るのが大変ではないですか?
渡利
履き続けた先を見据えての話ですが、価格のことを考える一方で「良く履く靴だからこそ、長く履ける靴でありたい」。そっちのバランスも考えていて
江川
…口調から察するに、価格とのバランスより「履きやすさ」と「長く履ける」この2つのバランスの方が大変そうですね
渡利
そうやね(笑)そのための見えない部分の仕様は吟味してるけど、バランスを取ることは簡単じゃない。
例えば、長く履くためにはアウトソールの耐久性が高いものでなければならないですよね。でもそれって、物としての重量は重くなるんです。それは快適性を失うことにつながります。反対に軽量のアウトソールを使用すると、耐久性が犠牲になって、早く削れてしまうというデメリットがでてくる。だからこそ、「履き心地のよさと長く履けるバランス」の答えの出し方はブルーオーバーの特徴であるような気もしています。まぁ、見えなくてわかりづらいんですけど(笑)

江川
そういう要素って得てしてトレードオフというか。特に靴はハードな使い方を考慮するとあっちが立てばこっちが立たない、なんてことになりがちですよね。歩きやすさも長く履けることも両方大事にすると、相反する要素を詰めこむことになってしまう。
でもどちらかを取って片方を捨てるのではなくて、ブルーオーバーは良い塩梅を常に探し出していて、長く履けるようにもしてるけど、快適な履き心地も追及している。という認識でいいですかね?
渡利
(笑)はい。そうとしか言えない…
快適であること
私は、靴というモノはとても不思議な製品だと思うことがあります。靴は履く人の体を外の世界とつなげ、運ぶ道具です。身体と地面を繋げる境界線を跨ぐ、唯一無二の存在とも言えます。楽しい時も、つらい時も、どんな時も常に時間を共有し、その人のありのままを受け入れます。そんな靴というモノに、私は特別こころ惹かれていました。
私は時折、高校時代に大切に履いていた靴を眺めることがあるのですが、その当時の記憶を思い出すことがあります。記憶とともに蘇る感情は、懐かしさだけではなく、愛情にも似た感情です。履き込まれた靴は、文字通り、苦楽を共にした友のように感じるからでしょうか。ブルーオーバーも、履く人が思い出を重ねていくことができるように、つねに履いていたい思ってもらえる、快適な履き心地をめざして設計しています。
江川
ここを読んでみると、確かに靴って不思議な感じがしますね。ある種、乗り物みたいな。車とかに近いのかな?
なんていうか…人によっては、靴は履ければいい、車は動けばいい、と考える一方で、いやこの靴がいいんだ、この車の乗り心地がいいんだって、こだわる人もいる。しかも、一緒に移動するからその分思い出もできる。そんなところが似てるような
渡利
うーむ。たしかに。そういわれてみれば、似てる気がするな
江川
渡利さんも、なかなかお目にかかれない車に乗ってますしね
渡利
そうやね、愛車のシティはちょっと不便だけど、それでも乗ってるのは気分があがるから。不便なとこには目をつむって、お気に入りの要素だけ見て選んだ。
靴も車も外に出かけて乗ったら最後、戻ってくるまでお付き合いしないといけない。履き終えたあとのお疲れさん感もあるよね。たしかに両方、そういった部分に愛着わくように思えるな
江川
……。
渡利さんにウケるかなと思って車の例え出したんですけど、実は車乗れないんですよね、わたし
渡利
のらんのかーい!
江川
あはは。いやでも、話しに出た「お疲れさん感」は、わたしも感じます。持ち物の中でも靴は、なんか愛着湧いちゃって簡単には手放しにくいし。手入れしてまだ履けないかな?って
渡利
僕が高校時代履いていた、サイドの穴がなぜかちっさいボロボロに履きこまれたスタンスミス(本物だとおもう)は、今でもお家にひっそりと飾っております。ヴィンテージでもなんでもないので、人が見たら、ただのボロボロのスニーカーなんやけど。完全に僕だけの思い出ですわ

長く履けること
履き込まれた靴には、人の油分や、自然にさらされることで生まれる手沢やなれといった味わいがあらわれます。長く履き続けられるように作られた靴というのは、その時間分だけ手入れが行われ、よりたくさんの味わいをまとうことになります。手入れの行き届いた靴を前に、私はそこに豊かさを感じとります。
江川
この部分を読んで大きく頷いたんですけど、真っさらな靴は勿論かっこいいけど、大切に履かれている靴は、格別の雰囲気がありますよね。
雑誌を見ていて、この靴素敵だな~と思ってクレジットを見たら、新しい衣装の靴じゃなくて、モデルさんやスタイリストさんの私物だったりする、あの感じというか
渡利
僕も、手入れされ履きこまれた靴の姿ってめっちゃカッコいいなって思うんですよ。ブーツや革靴なんか特に。あーカッコいいなーっておもいますね。人はかっこよく年をとりたいっていいますけど、靴にもかっこよく年をとってほしい。だから、そんな風に育つスニーカーをつくりたいんですよね
江川
折角長く使えるように作っているわけですし、子どもができて、その子にブルーオーバーが履き継がれるとかできたら、すごくいい感じですよね
渡利
そんなん最高やね!
感覚的ではありますが、ものを大切にするということは、そのものだけではなく自分自身にも心地よさ、やすらぎ、あたたかさを与えてくれるのではないでしょうか。ブルーオーバーが長く履き続けられる靴であるということは、履くほどに表情豊かになり、履き続ける人にこころの豊かさを与えてくれるようなものであろうと思えます。
江川
心の余裕があるから、身の回り品を大切にできる。のではなくて、身の周りの物を大切にすることがやすらぎや心地よさに繋がっているってことでしょうか
渡利
そうでありたいとも思っています。靴に限らず、モノというのは多くの人の手でうみだされた結晶のようなもので、モノを通じて作る人と使う人のコミュニケーションをとる媒介とも考えています。モノをモノとしてみるのではなく、モノを通してヒトをみる。そういう気持ちを抱くことで、豊かさの種を見つけててもらえたらいいなと思っています

江川
履く人に、大切にするだけの価値があると感じてもらえるような…ブルーオーバーは、そんな靴作りをしていくということですね
あたりまえで特別なくつ
ブルーオーバーは、健全な美を持つ靴を目指しています。それを履くことで、その人と靴の関係は、あたりまえでありながらもすこし特別な関係になりえます。地域社会で継承され続けた製靴産業や文化、そこに従事する人達を守り、育てることの一端を担い、自らも健全な循環の一部となることを示します。
江川
ここまで、かなりの時間を費やしてブルーオーバーのコンセプト文について話を聞いてきましたが、ハイライトの1つに選ぶとすれば、2回目に話題にした「ブルーオーバーは民藝じゃない」ってところだと思うんですよね
渡利
確かに。ブランドスタート以来10年間、ことある毎に「民藝」という言葉を使っていただけにね
江川
ただ、影響は強く受けてるんですよね。姿形じゃなく、「民藝」の成り立ちや背景の部分に
渡利
そうそう
江川
ということは、ブルーオーバーが内包している価値も、外観に現れるものだけじゃなくて、その背景込みで…なんというか、単に靴を履くというよりは、もう靴の成り立ちごと纏ってもらいたい。ということになってくるんでしょうか
渡利
そうですね。ブルーオーバーという靴とブランドを通じて、作っている人どうしのつながりや地域に根付く産業や文化を知ってもらって、応援してもらえればいいなと思ってて。過去から続いてきた物作りとその歴史は、産地の自然から影響を受けて共生してきたし、それ自体が「人の営み」だった。民藝という概念に感じる美というものは、そういう意味で人間として感覚的に心地が良いと思えるからこそ美しいのかなとも思っています

江川
最近、製品ページの一部にパーツ毎の産地を明記していますが、これはコンセプト文にある履く人 「自らも健全な循環の一部になる」 ということに根差した動きですよね?
渡利
うん。「自らも健全な循環の一部に」という言葉は少し難解な表現だけど、もっとシンプルに考えて、靴をコツコツ作ってきた地域を応援する。そう思って履くと自分も気持ちよくなれる。そんな風に受け取ってもらえたらなと
江川
そうですね。大切にしたい。応援したい。って思いを、履いてくださる皆さんの中に…なんていうか、喚起したいですね
物質的な豊かさではなく、精神的な豊かさを享受し、毎日を共にしてゆきます。手入れや修理を重ね、大切に履き続けられることにより、やがてブルーオーバーは「本当の姿」へと生まれかわることを信じています。履く人の時間とともに、自然が作り上げた味わいが深まり、友のような、あたりまえで特別な存在になることでしょう。
江川
この部分、本当にブルーオーバーらしいなと思うと同時に、思い切った表現ですよね
渡利
思い切った表現…? どこの部分?
江川
靴が新品の時じゃなくて、大切に履き続けてもらっている時こそが、ブルーオーバーの「本当の姿」だという…
渡利
自分の中ではずっとそう思ってて。ブルーオーバーの「本当の姿」とは、長く履きこまれて味わいのある靴であると同時に、履く人自身が成長したときの足跡として、その過程を呼び起こす存在になったときのこと。ともにした時間を大切にできた証として
江川
深いですね
渡利
そういった意味で、靴が製品として完成した時が終わりではなく、履いている最中もブルーオーバーの物語は続いているんです
江川
なるほど~。それが『履いてくださる皆さまへ』伝えたいことなんですね
渡利
実はそれだけじゃなくて。僕は、使う人(履く人)が自分自身を認めれるようなモノを作りたいと常々思っています。「自己肯定」といってもいいかな
江川
自己肯定、ですか
渡利
今は様々な情報にあふれ、信用するということ自体にエネルギーを使うしね。そういった世界の中で信じられるモノ。品質だけでなく、ブランドとして信じられるコト。そして持つ人がこれをえらんでよかったんだと思えるブランドでありたい
江川
情報過多な中で、靴に関してはブルーオーバーを履いていればもう迷わなくていいんだ!っていうような、ある種お守りみたいな存在になるということですね?
確かに、そういう物選びをすれば基礎みたいなものがしっかりしてきそうというか。自分を気分よく維持できそうです
渡利
今は多様性の社会であり、個人が自身の主張を発信できる。それは凄く良いことである反面、あまりにも増えすぎた情報によって、欲しい情報が見えにくくなったという側面もある
江川
難しい部分ですよね
渡利
であれば、僕自身がこうやってお話ししてどんなことを考えてブルーオーバーを進めているかを伝えようと思いました
江川
この連載の主旨そのものでもありますが、沢山の中の一つになってしまったとしても、声を届けない理由にはならないってことですね

ブルーオーバーを履く意味
私はこの靴を履いていただく人に、健全な精神を宿すと共に、おだやかであたたかい時間を過ごせるような機会となればうれしいと考えています。
江川
まあ、まとめると…ブルーオーバーという靴は履き心地だけでなく、気分も心地よくなるってことですね?(笑)
渡利
そうであれば嬉しいですね。ブルーオーバーの背景を知ってもらって、履いてもらう。物としてはあたりまえに「歩く」ことに注力した靴だけど、ブランドの想いを知ったうえで選んでもらうことで少しだけ気持ちよく暮らしていけるし、心地よく暮らすためのアンテナの感度もよくなる。これまでの生活の景色が少しだけ変わる。そんな感覚だね
江川
生活の景色ですか。自分が身に着けている靴、だけじゃなくて着ている服、使っている家具なんかにも、それを作っている人達がいるんだと気付いて物選びの基準にすると、確かに景色が違って見えるかもしれませんね。ブルーオーバーのコンテンツを通して、そんな風に感じてもらえると良いですよね
渡利
まあねぇ。ここまで突っ込んで話すことなんてないから、自分で言ってて気恥ずかしいけど…
これまでの製靴技術の蓄積とそれらを受け継ぐ人。そして彼等からうまれた靴を履く人へ。ブルーオーバーは、日本でうまれた健全で美しいスニーカーでありたい。そして履く人の時間と共に形づくられ、あなたにとって思い出深く、とても美しい靴となってほしいと願っています。
渡利
ブルーオーバーはどこにでもあるような靴ですが、ただの靴ではない。そんな風に思われたい。僕たちは靴を通じて、人や文化のレガシーを残していくこと、履く人にも脈々と受け継がれた日本人のアイデンティティを通して美しさを感じてもらいたい。そのためには僕たちの靴自体も健全で美しく、長く履いていけるように作らなければならないと考えています
江川
そうですね。それこそ、モノや情報があふれているこの時代、ブルーオーバーのようなスニーカーを見つけてもらったり、良さを感じてもらうことは簡単じゃないというのが本音ですが…
渡利
まあね
江川
でも、それが発信しないことの理由にはならないですから。今回、渡利さんから直接ブルーオーバーへの想いを聞くことができました。この想いが応援いただいているお客様に届けばいいなと思います。旗艦店ストラクトでも、店長の原田さんからどんどん伝わっていくといいですね!
渡利
ですね。本当に10年、応援していただいているお客様があってのブランドだし
江川
大切に履いてもらっている時こそ、ブルーオーバーの「本当」の姿になる…つまり、履いてくださるお客様あってのブルーオーバーということですね。また、ここまで読んでくださった皆さん、ありがとうございました!
渡利
ありがとうございました