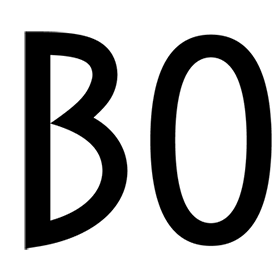ANONYMOUS EMBODIMENT
この執筆は2025年の周年記念に配布された冊子に掲載されたものになります。まだお手元にない方にも読んでいただけるように、今回サイトにて掲載することになりました。
2026年1月1日
はじめに
昨年から、ブランドに対する考え方を、アカデミックな視点から言語化する取り組みを行っていました。これまでも自分なりに文章化はしてきましたが、客観的にそれがどのように見えるのか、非常に興味がありました。そこで、友人の紹介からライターの室越龍之介さんへ依頼。室越さんは人類学を専攻、キューバなどでフィールドワークを行っていた方です。僕自身が文化人類学に興味を持っていたこともあり、室越さんに依頼して、その文化人類学の手法を自分に向けてみたときに何が出てくるのだろうか、という期待がありました。
まず、室越さんによる僕へのヒアリングを実施。初日はヒアリングと、その後の食事を合わせて、延べ8時間以上にも及びました。後日、blueoverの立ち上げメンバーへのヒアリング、そして再度私との打ち合わせを重ねました。その結果は、十二分に満足できるものでした。文字数は延べ10,000字。このような形で自分の考えを整理してもらうのは、奇妙な感覚であると同時に、自分では気づかなかったものを可視化できたように思います。
室越さん曰く、文の構成は「日本的な論証とフランス的な論証が混ざった感じで、『抽象的世界』というテーゼに対し、『具体的世界』というテーゼを持ち込んでいるところが弁証法的」とのこと。「(ジン・テーゼとしてもう少し話を厚く書いてもよかったかもですね…)最後が『具体的世界』に突入することでの変化、という書き方をしているのが、日本的な部分のように思います」と。確かに、弁証法として現代における経済合理性と、それに対する非合理性を展開し、その先の可能性を見出そうとする展開は、自分自身も気づかなかったものに気づかせていただくことができ、今後のブランドの方向性に大きな影響を与えるものでした。
こうして言語化された文章が2024年末に完成。タイミング的にもちょうど良いということで、今回のポップアップストアで配布する冊子の中に「anonymous embodiment」と題された考察を掲載することとなりました。それが今、皆様が手に取ってくださっている、この冊子です。
blueoverは、とても小さな国産スニーカーブランドです。しかし、そのスニーカーには、履く人にとっては機能的な価値だけではない、特別な何かが込められています。今回初めてblueoverを知ったという方も多くいらっしゃると思います。そういった方々に向けて、本誌ではブランドの基本的な考え方も掲載しておりますので、これを機に、日本にこのようなスニーカーブランドがあるのだと知っていただければ、大変嬉しく思います。
2025年2月末日

anonymous embodiment
室越龍之介
blueoverという問い
blueoverの靴は、そっと置かれた僕たちの社会への問いである。
「僕たちの社会」と言ったとき、そこの想像されているものが四つある。
一つ目は、グローバルであること。今日、僕たちは地球全体に張り巡らされた商品(コモディティ)のネットワークとともに生活している。寿司を食べるとき、そこにはインド洋で獲れたマグロ、チリで養殖されたトラウト(サケ)、モザンビークで水揚げされたタコが使われている。パキスタンで栽培された綿花がインドで布になり、ベトナムで縫製されて、洋服として僕たちの手元に届く。カリフォルニアでデザインされ、台湾で生産された部品を使い、中国で組み立てられたスマートフォンを使う。僕たちはコモディティを介して、世界中と繋がっている。
二つ目は、工業的であること。それは大量生産をすることでもある。巨大な消費に応えようと、コモディティが大量生産される。大量生産を可能にするのは機械だ。機械を用いるには、材料や部品や製品を企画化する必要がある。無限とも思える大量の製品を寸分違わず生み出すことができる工場。そして、規格化された製品はどこでも買うことができる。大阪でも東京でもコカ・コーラは飲める。ロシアでもキューバでも飲める。だいたい似通ったものを場所や時間に制限されることなくいつでも手に入れることができる。
三つ目は、主流つまりメインストリームであること。そして、メインストリームを中心とした価値の体系があること。どのようなものに価値があり、どのようなものに価値がないのか、という僕たちの持つ共通観念がある。価値を何かに置くということは何かに価値を置かないことを意味する。したがって、「何かを良い」と考えることは序列を生み出す。さらに、「みんなが何かを良い」と考えれば社会の中で「みんなが良い」と考えるものを中心とした価値の序列ができる。例えば、それが一過性のものであれば、流行と呼んでもよいだろう。だが、みんなが良いと比較的長い時間中で考えると、価値のヒエラルキーを作り出すメインストリームが現れる。
四つ目は、抽象的であることだ。僕たちは社会のなかで具体的な一個人としてあまり扱われない。会社の中では従業員として扱われるし、家庭の中では親や子として扱われる。消費をするときも何かを審美して、選ぶ主体として扱われるより、コモディティを売り込むためのターゲットとして扱われる。僕たち自身でなく、男性とか女性とか、あるいは30代とか40代とか、都会的なライフスタイルの持ち主としてであったり、アウトドア愛好家としてであったり。自分自身であるよりも、消費者として扱われる。僕たちは、具体的な世界に生きているのに、世界を見る時は抽象化して受け取っている。

blueoverはこの四つの想像力への抵抗として存在する。
グローバルではなくローカルであり、工業的ではなく工芸的であり、主流ではなく独自であり、抽象的ではなく具体的だ。
さて、その四つの想像力にblueoverがどのように応答しているか、見てきたい。
「交換」を考える
blueoverのブランドストーリーで、デザイナーの渡利ヒトシは、「プロダクトデザインの仕事を請負う中で、製品開発、消費のサイクルに疑問を持ちはじめていました」と書いている。
資本主義の仕組みの中にあっては、利潤を上げることが至上命題となりやすい。そして、利潤に基づいた合理性が発揮される。利潤を上げようとすると、消費者により多くの消費を促す必要がある。そのためには、新しい商品を投入し、消費者を刺激しなくてはならない。そして、製品を開発し、消費までのサイクルを短くし、その短い時間の中で大量の製品を生産することが合理的である、ということになる。このサイクルの「速さ」に渡利は疑問を持ったわけだ。
その疑問は理解できる。利潤に基づいた合理性は僕たちにとって唯一の倫理に見えるのだが、人類社会を広く見渡してみると、実は僕たちの社会に固有の、ある意味で特別な考え方であることがわかるからだ。
例えば、マルセル・モースはその著書『贈与論』の中で、僕たちが行う売買(交換)よりも、贈与を介した交換(贈与交換)の方が人類にとって一般的なものを手に入れる手段だと主張した。
モースによれば、多くの社会では、贈り物を与える義務、受け取る義務、そして返礼する義務があるという。義務は社会のなかにダイナミクスを生み出す。だいぶ廃れてしまっているが、日本にもお中元やお歳暮といった贈答の習慣がある。お中元やお歳暮はお世話になった人への感謝として半ば強制される、つまり義務であっただろう。そうやって感謝の印として贈られた品を断ることは、失礼に当たるというのも大方の感覚でわかるのではないだろうか。そして、贈り物が届けば、自分もまた贈り物を返さなければならない。
僕たちの社会でお中元の習慣が廃れていっていることからわかるように、贈答は面倒臭いものだ。欲しくもないものを受け取り、コストをかけて与えなければならない。その結果として、僕たちは何も得られない。
だが、モースは実は僕たちは贈答品の他に贈与を通して得ているものがある。それが人間関係だ。贈り物をすれば相手と仲良くなれる。つまり、人間関係が結ばれるのだ。モノの交換は人間と人間を結びつける力がある。それは、必ずしもポジティブな結び付け方だけではない。北米先住民においては、贈与に対し、返礼ができなかった場合、奴隷になるという習慣があった。モノの交換は、そのように人間同士を結びつけることもある。
カール・ポランニは、贈与と交換という二つの分け方ではなく、「互酬」「再分配」「交換」の三つの分類を置いた。互酬は贈与をし合うことによって生まれる相互扶助の関係、再分配は権力の中心に対する義務的支払いと中心からの払い戻しを行うことで、中心と周縁という権力構造を生み出す。交換は僕たちの社会の売買に近い。市場における財やサービスの運動だ。
面白いのは、互酬が比較的平等な、再分配が比較的ヒエラルキー的な人間関係を生み出すに対し、交換は人間関係をその場限りのものとして精算できると考えている点だ。
実は、日本人の文化的特性について研究した『菊と刀』の著者、ルース・ベネディクトも似たようなことをいっている。ベネディクトによれば、日本人のモノのやりとりは、「義理」「恩」「交換」の三種類でなりったているという。義理は互酬に、恩は再分配に、交換は交換に対応している。

これらの学説を踏まえると、お中元やお歳暮の衰退は、僕たちは義理や恩の世界から純粋な交換の世界に行こうとしているからであるように思える。
純粋な交換の世界では、抽象化された無数の無名の人間が抽象化された無数の無名の人間とモノの交換だけで媒介さる。
僕たちは普段の生活の中で、コモディティがどこからやってきたのかを気にしたりしない。誰が作ったのか、誰がデザインしたのかも。ヒトやモノを機能として捉え、その具体的な固有性について思いを巡らしたりしない。交換によって手に入れたものは、そういうことを考えなくて良いようになっている。
なので、「消費のサイクルに疑問を持つ」とは、この売買が消費者をつなぎ、どこにも具体的な人間が存在しない世界に疑問を持つということであるとも解釈できる。そして、この疑問は市場での売買にどこか贈与の部分を想起させることにつながりうる。
贈与されたものは、他では手に入らない。 花屋で購入したバラの花が萎れてしまえば、また花屋で買えば良い。別の花屋で買っても良い。だけれども、恋人からもらったバラが萎れてしまえば、それを別のバラで取り替えることはできない。「恋人からもらったバラ」は恋人と自分との関係の中で生まれた特別な意味が付与されているからだ。
つまり、あるコモディティを買う、という行為がある人間と別の人間とを繋ぐことで特別な意味を生み出すことができれば、単に取り替え可能なコモディティは固有の具体的なモノになる。 とすると、「誰かから買う」という行為が個別の価値を生む特殊な振る舞いになりうる。
従って、こういうことになるだろう。
普通は、消費者にとって、ブランドも靴も、代替可能、選択可能なコモディティに過ぎない。消費者とコモディティもしくは、消費者とブランドはなんら特別な関係で結ばれていない。だから、消費者はさらに強い刺激を受けると、すぐに靴を買い替える。新しいデザイン、新しい機能、新しい付加価値が提示されれば、消費者はそれに反応してしまう。
だけれどもblueoverの靴はこのようには提示されていないように見える。
blueoverの靴を買うとき、購買者がblueoverの靴と固有の関係を結ぶことが期待されている。それは、直営店structの店長原田やその他の店員との関係かもしれないし、デザイナーの渡利との関係かもしれない。もしくは靴そのものに込められたメッセージが、購買者に具体的な関係性を感じさせるのかもしれない。

具体的に関係性が結ばれた靴は、代替可能、選択可能なコモディティではなくなる。
取り替えが効かない。
購買者はその靴と関係性を発展させていくしかない。
贈与をひとたび受け取ってしまえば、返礼をし、そしてまた贈与を受けるように。
そして、購買者と靴の関係が発展すればするほど、購買のサイクルは遅くなる。
すると、製品開発と生産のサイクルにも変化がもたらされる。
そのような企みが、存在しているのではないだろうか。
それはblueoverの靴を通しても見えてきそうだ。
なので、次はデザインについて考えてみよう。
「用の美」と匿名的な靴
blueoverではじめに作られた靴、「マイキー」は靴のイメージそのものといっても良いような形をしている。 渡利はそのデザインを「アノニマスな(匿名的な)」と呼んだ。匿名的であること。「その製品が誰によって作られたかわからない」ことが大切であるらしい。
この発想は、渡利が影響を受けた、民藝の概念と「用の美」にも通じているだろう。
その土地で働く名もなき職人たちの手仕事から生まれる、土地に根ざしたデザイン。そして、その道具の用い方に則した、過不足がないデザイン。
マイキーはまさにそういった形をしている。
マイキーを見ていて想起するのは、ある木こりの木挽き鋸の話である。
僕はこの話を民俗学者の香月洋一郎先生から直接伺ったので、話自体には記憶違いがあるかもしれない。曖昧な記憶を手繰り寄せて話すとこのような話だ。
香月先生のチームは、各地から木挽き鋸を収集していた。林業も工業化され、チェーンソーが導入されていたので、民具(土地の人々の日常遣いする道具)が散逸しないように集めて保管していたのだ。
何百本という鋸が収集されたので、古い木こりに頼んで、その分類を手伝ってもらっていたらしい。その木こりの爺さんがある鋸を手に取り、「この鋸の持ち主は幸せな人生ではなかっただろう」と言ったという。
香月先生は不思議に思ってなぜそう思うのか尋ねた。
木こりは返事をして、 「この鋸は手入れが行き届いている。腕の良い職人だっただろう。だが、古いのにあまり刃が減っていない。このように細かいところまで手入れが徹底しているような神経の細かい人は周りとうまくいかず、職場を転々としたはずだ。だから、腕の良さに対して、刃の減りが少ない」と答えたという。
モノには必ず来歴がある。目利きが見れば、その来歴がわかる。
古い木こりには、鋸の所有者の顔も名前もわからないが、どういう人物であったのかわかった。
つまり、匿名のモノからそこに携わった具体的人間を洞察したのである。
さて、古い木こりが鋸を見たように、僕たちもマイキーを見てみよう。
ブランドは大阪市福島の莫大小会館の地下で生まれた。
ブランドの立ち上げチームは渡利の育った大阪の人間関係の中から立ち現れた。渡利は若い時から自分のスペースに人を招いてゲームをしていたという。そのゲーム仲間、そして、一緒に仕事した仲間でチームを立ち上げた。
無数の人間が貯蔵される人材プールからリクルートしたわけではない。
渡利が自分の人間関係の中から立ち上げたチームだった。
どれほど売買が優位の社会であっても、僕たちは日常生活を抽象的な人間として生きているわけではない。親兄弟もいれば友達もいる。偶然の出会いがあり、別れがある。個別の人間が個別の人間に出会う。
デザイナーが小売の店長と出会うわけではない。起業家が従業員と出会うわけではない。そのようにしてチームが立ち上がったのではなかった。ゲーム部屋の中から、仕事仲間からチームが生まれたのである。
渡利が作ろうとしたのは、靴だった。
そして、それは「100%国産の」靴だった。
blueoverというブランド名も、日本から海を超えて世界に、という意味が込められていたと聞く。
国産の靴はやはり資本主義の合理性からすると、妙な発想ということになる。
外国で作った方が安く、早い。交渉や大量生産に慣れている海外の工場と仕事をすれば、いち早く合理的なコモディティが作れたはずだからだ。
社会のメインストリームはそのように動いた。2000年代の不況で、多くの靴メーカーは生産拠点をアジアに移していった。コストカット競争は加速し、国内に残った小規模の工場はますます厳しい状況に追いやられた。
2011年の立ち上げはこの状況へ対応しようとするものだった。モノヅクリに携わってきたプロダクトデザイナーとして、日本における靴産業が稼働し続けられるよう企んだのだ。
この企みの背景にあるのは、やはり渡利がフリーランスのデザイナーとして、さまざまな工場に出入りしてきた人間関係だ。具体的な「渡利の人間関係としての日本の製造業」を支えるプロダクトとして、マイキーは生まれたわけだ。
ブランドの立ち上げチームにしても、サプライチェーンにしても日本中あるいは、世界中のオプションから最適なものを選ぶ、という選択もあったはずだ。つまり、「渡利の作りたい靴」を売る事業を前提条件として、マーケターや生産管理者、営業や工場を選定しても良かったはずだ。
だけれども、「渡利の作りたい靴」はすべてを規定する前提条件というより、人々のネットワークを浮かび上がらせる触媒のような働きをしたようだ。
渡利の人間関係がまず存在し、「渡利の作りたい靴」というプロジェクトが立ち上がることで、参画する人たちがそこから立ち現れた。
利益の追求目指しての商品の企画、効率的な生産とそのための人材の配置、というようなある種の理想的な計画とは逆向きだ。
まず、人間の関係があり、そこにプロジェクトの動機を投げ込む。すると、人間関係の中でそれぞれができることを動員して、商品を作り出し、その商品は具体的なモノとして購買者に行き着くことで結果として利益を生む。
生産工程のほとんどがローカルとして、具体的な人間関係の連なりと一致する。
日本語では売買の営みのことを「商い」という。この言葉の語源には諸説あるというが、間に立つ意味の“空く”が変化したとする説や、双方の満足・充足を意味する“飽く”が変化したとする説があるらしい。
とすると、blueoverの仕事というのは、靴を通した人々の間にたって、そのつながりを見通して、利益を差配していくという意味でまさに商いであると言える。
鋸の刃に職人の人間性が宿ったように、blueoverの靴には渡利が媒介した膨大な具体的な個人の手触りがある。そして、それを特段に意識しなくても良い匿名性がある。

(非)合理的な選択
このような事業のあり方は、「非合理的だ」と渡利は考えている。周囲からのそのような指摘もされるらしい。
今日、僕たちの社会では「利潤の追求」をゴールに置き、ほかの決断はゴールに向かう従属項目になりがちだ。すべての従属的な決断は利潤の追求という目的に沿って効率化される。市場経済において、人間が抽象化されてしまうのはそのためだ。人間を量的に分析・操作が可能な「労働力」や「購買力」として扱うことで初めて、利潤の追求を巡る一連の行為の決断が可能になる。
ある具体的な個人がいたとして、その人の体型も独特であれば、育った環境や政治思想、食の好み、職業や年齢、体調といった組み合わせも独特である。一人として同じ人はいない。例えば、「40〜50代男性」をターゲットとしたとき、それはターゲッティングをする人たちが考える想像された「40〜50代男性」が立ち現れるに過ぎない。具体的な「40〜50代男性」はその想像より、多様かつバラバラで「40〜50代男性」以外の特徴で同じ集団を抽出することはほとんどできないような人々だろう。にもかかわらず、想像されたターゲットの振る舞いをさらに想定する。
予断に予断を重ねるような行為が正当化されるのは、「利潤の追求」という合理性を下支えする基盤が必要だからだ。思うに、このような予断に満ちた想定抜きに、実は合理性というものは立ち現れない。
僕たちは一般に、「合理性」というものを普遍の事実だと考えがちである。多様な人々が多様なものの見方を持っていたとしても、それらとは違った、客観的で合理的なものの見方が存在すると考えている。合理性はこの意味で特権的なものの見方となってしまう。
言い換えれば、合理的であることは唯一の正解となることができるわけだ。この視点に立てば、非合理的であることは、不正解であり、そのような視点に立つ人々を「愚かな人々」だと考えざるをえないという事態に陥る。
だけれども、blueoverの試みは時代のメインストリームとはそれほど合致しないながらも、奇妙なことに破綻せず継続している。
となると資本主義下での経済活動としても「間違って」いるわけではないということになる。
これをどのように考えたらいいだろうか。
文化人類学では、他者の合理性を考える。
この学問の黎明期には、異文化に生きる人々を「未開」あるいは「野蛮」な人々と考え、人間はいずれ西欧人のように「文明」的になると考えていた。劣った人々に文明と教育を与えるという名目で植民地主義も肯定された。優れた人々が劣った人々を支配するという考え方が当たり前だった。
この考え方に異を唱えたのはドイツ生まれで、アメリカで研究生活を送ったフランツ・ボアズだった。
ボアズと同時代まで、多くの人類学者は植民地に送り込んだ植民地行政官や探検家から送られてくる資料をもとにさまざまな分析を行い、理論を打ち立てていた。ボアズは、こういった「ゆり椅子」に座ったままの研究者と異なり、北米大陸でネイティブアメリカンの調査のためのフィールドワークを行い、現地の人々と直接対面した。
直接体験した生の経験を得て、ボアズは「未開人」たちは西欧とは異なっているもの、劣っているわけでも遅れているわけでもないという認識を持った。それぞれの文化はそれぞれの歴史的背景に基づいた独自の合理性に基づいて形作られているわけだ。
合理性は一つでもなく、特権的な地位を占めているわけでもない。
前提条件を変えれば、また別の合理性が立ち現れる。
このように考えると、「利潤の追求」を前提とした合理性もやはり相対化され得る。
「利潤の追求」においては、人間を抽象的に捉え、カテゴリー化することで操作可能な対象と想像する。このような想定力が効率化を可能とする。不確実な未来から逆算した「効率」が成立するためには、「人間が操作可能な対象である」という想像力が不可欠なのだ。
このような想定は、大量に生産されたコモディティを大量に消費するときには、機能するかもしれない。だが、例えば、絵画を買おうとするとき、僕たちはそのような購買行動をするだろうか。絵画に限らない。骨董や工芸品を選ぶとき、僕たちはモノを消費しようとするわけではない。そのモノの持つ機能を超えて、モノとの新しい関係を取り結ぼうとする。
ある絵画を買う時、どの絵画だって構わないということはないだろう。「この絵なら買いたい」と思わなければ絵画を買おうとはならないのではないだろうか。皿を買う時もそうだ。皿一般を買おうとするのではない。その皿に盛り付ける料理、季節、場所を想定し、それに見合った皿を探すはずだ。
blueoverの靴はこの意味で工芸的なプロダクトのように思える。正確には、blueoverの靴は工場制手工業(マニファクチュア)のプロダクトだ。一品一品手作りする工芸品とは違い、流通に乗せることが可能であるほどに生産を行っている。だけれども、そこで意図されているのは「遅い消費」だ。現在の利潤追求の消費サイクルに乗った消費を「速い消費」とするならば、モノと人の具体的関係で結ばれる、ゆるやかな消費サイクルの乗った消費は「遅い」。「遅い消費」という企図のなかでは、購買者が自分で靴との関係を取り結ぶことが期待されている。
この意味で、マイキーを買うことは絵画を買うことに近い。
では、合理性の話に戻ろう。
資本主義下においては、「利潤の追求」とそのための効率化を図ることが唯一の合理性だと考えられがちだった。だけれども、フランツ・ボアズは他にも合理的なあり方の存在を示唆していた。
blueoverは「利潤の追求」を資本主義における所与の条件と考えながらも、それを思考の起点には置いていない。思考の起点は、「モノと人との具体的な関係」だ。
このように考えると、「合理性」なるものが逆転してきはしないだろうか。
blueoverにおいて「利潤の追求」は必然の目的ではなく、意図の結果たまたまそうなった帰結となる。「効率性」は、大量に販売することよりも、購買者が特別な関係を結ぶに足るプロダクトを作ることに対して適用される。つまり、たくさんの小売店に大量に卸すというより、直営店structやウェブサイトを通して、自分たちのプロダクトがどのようなものであるか、繰り返し説明することが「合理的」で「効率的」な振る舞いとなる。
消費サイクルを鈍化することは、利潤の追求を諦めた非合理的判断ではなく、靴が媒介する人間関係全体に対する合理的な配慮となるというわけだ。

匿名的具体化
さて、靴の話に戻ろう。
匿名的であることを期待された靴が制作された。会社やブランドやデザイナーが消失し、ただどこからともなくやってきた靴として、買われることを期待された靴。なんの権威もなく、ただモノとしての存在を賭けてそこに売られている靴である。
木こりの鋸を思い出してほしい。鋸は匿名である。だけれども、強烈に持ち主のあり方を示唆した。
blueoverの靴も、購買者に誰とも知れない制作者を想起させる。なぜなら、その靴は製作者の思想を具体化したものだからだ。
「具体化」の英訳の一つは「embody」だ。emは「〜の中に」を表し、「body」はここでは「物質」を指す。つまり、語源的には物質化すること、なにか考えや概念を実際に行うことを示している。
渡利の考えたことが、靴として具現化している。そして、靴を通して、靴が媒介する人々の行動を変容させ、その認識に作用する。
匿名で発せられたメッセージが人々を突き動かすこともある。
1789年に発表された「第三身分とはなにか?」という匿名パンフレットは、フランス革命に向けて世論形成に大きな貢献があった。
匿名であるからこそ、そのメッセージが浮き立つ。
「誰が言ったのか?」ではなく、「何が言われているのか?」が大切になる。
これは、現代社会を回している、広告を通して脳の報酬系を刺激し、抽象的なプロダクトを買わせるのとはまったく異なったやり方だ。
靴を買うとき、どれだけの人が靴を見ているのだろうか。靴に貼り付けられたロゴを見ているのではないか。靴を買うとき、どれだけ店員を見ているだろうか。そこで交換される財だけを見ているのではないか。
blueoverの靴は、このように駆動する僕たちの社会に対して、「ほんとうに世界はそのようだろうか?」と問いかけている。
事実、僕たちは抽象的には生きていない。
渡利のゲーム部屋の仲間と同じように僕たちも友達を持ち、渡利と工場や職人たちとの関係と同じように、僕たちも顔も名前もわかる、家族構成や出身や食の好みを知った仕事仲間たちを持っている。
靴もまたそうだ。靴はただ「歩く」ために履かれるわけではない。
ある特定の道を特定の季節、特定の時間歩くとき、履かれている。
blueoverは控えめだ。
問いをそっと置いている。
それを問いと気づかなくても良いし、問いに答える必要もない。
僕たちは好きなように靴を買い、好きなように履くことができる。
だけれども、同時に一つの思想が匿名性の向こうには置かれており、僕たちは靴を通して、世界に応える可能性が与えられている。
blueoverの靴を履くとき、僕たちは「靴を履くこと」を問われる。
靴を履くことが僕たちにとって、どのような意味を持つのか。
靴を買うとき、靴を売る人や作る人達と僕たちがどのような関係になれるのか。
靴を所有することを通して、僕たちは世界をどのようなものだと見ているのか。
blueoverの靴を履く時、僕たちはモノを通した具体的な人間関係の網の目に踏み込んでいけるのだろう。

室越 龍之介 Murokoshi Ryunosuke
アンソロポロジスト、ライター。専攻は文化人類学。九州大学人間環境学府博士後期課程を単位取得退学後、在外公館やベンチャー企業の勤務を経て独立。個人ゼミ「le Tonneau」を主宰。法人向けのリサーチや経営者やコンサルタント向けに研修や勉強会を提供。Podcast番組「のらじお」「新日本駄洒落協会」を配信中。