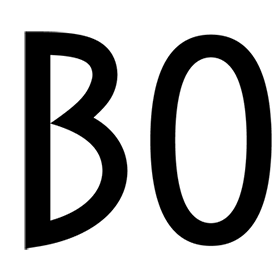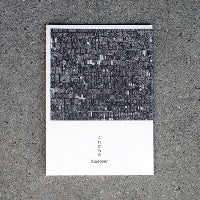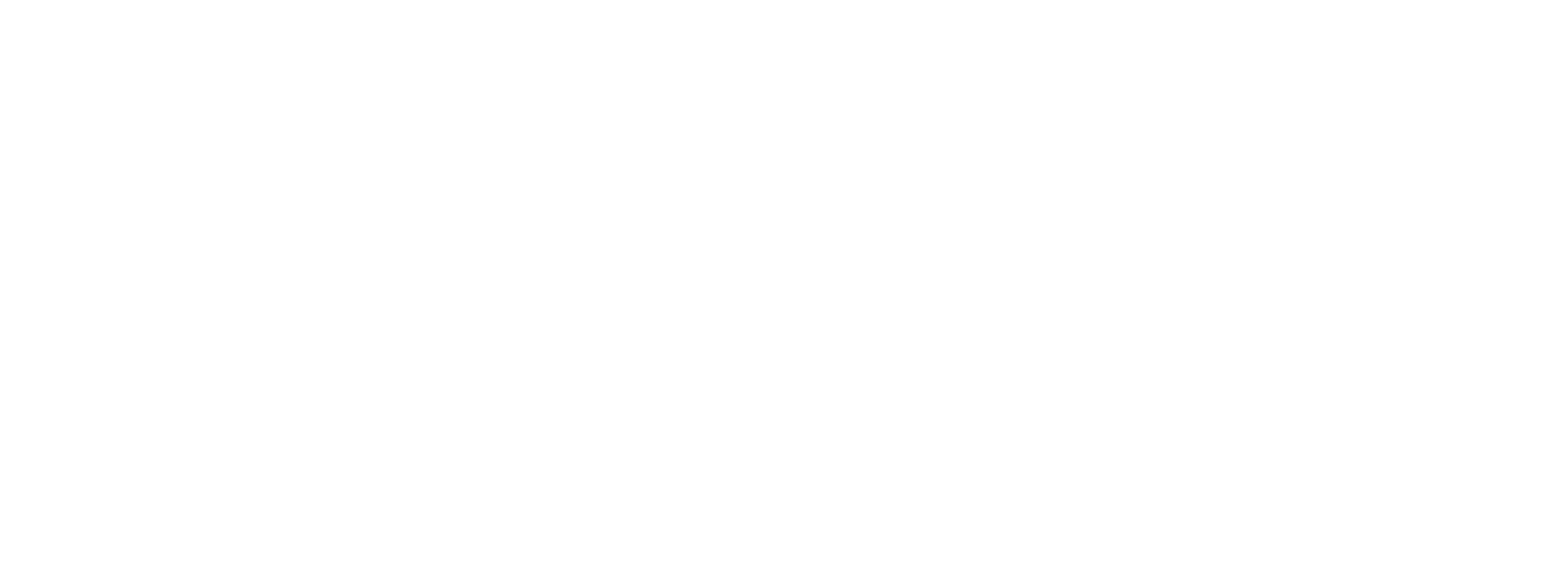これからのblueover
文:渡利ヒトシ(blueoverデザイナー)
はじめに
この執筆はもともと僕が自分の考えをまとめるために、Webメディアのnoteに書こうとしたものを、11周年という節目にあたって、冊子にしようという意見から生まれたものだ。なので、文章中に出てくる発言はあくまで自分の考えを整理するためのものであって、誰かに読んでもらおうと思って書いていないので、わかりにくい点があることを了承していただきたい。また、学術的やエビデンスにのっとったものではなく、個人の経験に沿った主観が強く、その点もご了承いただきたい。(22年6月3日)
追記:
この冊子を年末のゆっくりした時間に読んで頂きたいとおもい、サイトにて連載することになりました。この執筆のあと事業継承問題、アート、福祉について少しづつ学びながらblueoverの活動と重ねることを試してはいるのですが、なかなか思うように物事は運びません。ですが来年には何かしらblueoverの新しいチャレンジをお伝えすることが出来ると思います。
世界情勢、社会が不安定であるなか、自分たちが信じれること、伝えたいコト、出来ることを少しづつでも実行していきたいと考えています。私達は靴を作り、みなさまに履いていただくことを生業としおりますが、履いていただく方に、「靴を履く」ということだけでない価値を提供すること。その価値がこれからの社会にとって明るい状況を生み出すような結果になること、blueoverを履かれることで自身の新たな歩みが出来るようになればと考えています。
物事はすべてうまくいきませんが、それでもあきらめずに続けることに意味があると信じて、来年もまた歩んでいこうと思います。(22年12月11日)
いま考えていること
今、世の中は不安定な要素や解決すべき課題がたくさんある。けれど、自分たちの組織としてその課題にたいして何ができるか、どうするべきかを考え、実行する。これがまず大切なことだと思っている。
僕はもともとプロダクトデザインという仕事に就いて、企業と一緒に商品の企画やデザインを行っていた。それが15年前(2006年)に独立して、11年前(2011年)にブルーオーバーというスニーカーブランドを作った。今ではバトンという法人を経営して複数のブランドを展開するようになった。会社は少人数で売り上げ規模も小さいけれど、自分たちがしたいこと、良いと思えることができるような会社にしていきたいと考えている。
で、これから何を書いていくのかということだが、自分が今時点で描くブランドのあるべき姿を書いていくことにする。なかでも、10年前にデザインからモノウリのきっかけを作ったブルーオーバーについて書こうと思う。
そこでまず、ブルーオーバーについて簡単に説明しなければならないのだが、それはそれで長くなるので、こちらのアバウトから読んでいただければと思っている(コンセプトとしては結構長文)。
さて、最初にも書いたが、昨今は全世界的にとても不安定な世の中だ。これまで無かったような困難が国内においてもおきている。解決すべき課題は山積している。そんな中でもブルーオーバーはお客様からの支持を受けて続けることができた。そしてこの間に、僕たちはブランドの在り方や、生産体制、これからのことを会社の仲間とじっくりとたくさん話しあった。
他でも言われていることだが、本当に世の中にはモノがあふれている。店頭に置けば売れる時代はとうに過ぎ去り、様々な工夫を凝らして売っていかなければならない。それでも買ってもらうのは難しい。本当に人の消費行動が大きく変化し、モノにおける大量生産、大量消費の時代が終わりを迎えつつあるのを実感している。
国内生産
ブルーオーバーは国内製造の継続を一つの目的として、国内生産にこだわり続けている。その姿勢は今でも変わらない。だが、このブランドを続けてきたこの十年の間、実際にものづくりの現場へ足を運び、目にしてきたことで、ブランド発足当初とは、見える景色が異なるのも事実だ。
僕たちブルーオーバーはとても小さなブランドだ。僕らのような資本の少ない小規模ブランドは、小さい規模感でも持続可能な体制を作る必要がある。
通常、工場に生産を依頼する場合、必ず生産条件というものが存在し、最低生産数とその一個あたりの金額が提示される。
まずはこの条件を受け入れなければ、モノを作ることすらできない。以前はこの数字が大きく、自分たちのような小さなブランドが取り組むのにはなかなか厳しい条件だったのだが、近年では様々な工場が縮小傾向になり、それに伴い生産条件のハードルは下がってきている。この現状は自分たちにとっては都合は良いが、業界としては市場規模が下がっていくことを意味している。どっちが良いかという話ではないがこういった状況は起こっている。
そして、僕らの周りの製造業で働いている職人さんたちの年齢は65歳以上の高齢者である場合がほとんどだ。これは組織の若返りがうまくいっていないということだが、賃金の低下によって、若い人の雇用が生まれていないということとつながっている。
僕らとしても国内生産にこだわり続けたいという想いはあるのだが、想いだけでは継続できないという自覚もある。今ある製靴産業のビジネスモデルから脱却しなければいけないのは、明確だ。
そんな中で、若い人の新しい動きも目にするようになった。最近出会ったタンナー(革を鞣す工場)「セトウチレザー」だ。
このタンナーは30歳近い年齢の井上さんと江浪さんが立ち上げたのだが、ブランドを始めてこの10年、こんなにも若い人がタンナーを立ち上げたというのを聞いたのは初めてであり、驚きであった。
若いタンナー。それだけでも珍しいのだが、セトウチレザーは取引形態も少し変わっている。一般の消費者がタンナーと直接取引することはあまりなく、いわゆる革問屋と呼ばれる中間業者が存在しており、そこと取引することが多い。その理由だが、一般消費者は革を一枚からでも購入したいのだがタンナーでは基本、革を一枚売りという形をとらず、最低でも10枚前後からでしか取引ができない。そのため、革問屋が在庫を抱え、消費者はそこで一枚からでも購入することができるということだ。そしてタンナーは在庫を抱えないため、鞣した段階で完全買い取りという形をとっている。つまり、一般消費者がたんなーと取引することは専門性が高く、かつ希望通りの革が仕上がらなくても10枚から革を買い取らなければならないということである。
そういった理由で、タンナーは表舞台にはなかなか出にくいという理由があった。だが、このセトウチレザーは小売り機能を持たせ、ダイレクトにエンドユーザーとつながると同時に、消費者のオーダーに対して、明確な価格表というものを作り上げた。つまり、エンドユーザーに対してわかりやすい料金体系を提示して、不透明さを軽減させたということだ。そのようなビジネスモデルは業界にはなかったことだ。やはりこれまでのしがらみがない若い人が立ち上げたタンナーだけに、老舗にはない新しい形の革産業に感じられる。こうした取り組みは小さくもあるが、各地で少しづつ芽生え始めている。
こうした背景の中で自分たちの立ち位置は、少量であれど地域の工場が続く限り国内発注を続けながら、これまでの製靴産業とは異なる継続可能な生産体系を作り上げることだと考えている。僕が考えるのはホールガーメントや三次元プリントなどの、新しい生産方法に目を向けること。もう一つは従来のマシンメイド(ミシンを使った人の手による縫製)を維持できるような雇用形態を見つけることだと考える。ホールガーメントなどの技術革新による生産方法は、環境コストも人的コストも軽減されることが前提として考えられる手法なので、実現可能な状況がくれば、積極的に取り入れたいと考えている。
だが、ミシンを使ったマシンメイドは、人の手が必ず必要だ。だが縫製業は高齢化と工賃低下から、どんどん縫子が減少している。縫製だけで見ると、バッグや服といった縫製もあるが、業界としては同じ縫製でもスキルや機械の種類が異なるので、依頼することは簡単ではない。経験上不可能である。
一般的に産地地域の問屋制家内工業と呼ばれる生産体系は、問屋(ここではブランドを所持している会社)からのオーダーをもとに、地域をまとめている胴元がおり、そこから縫製場に割り振ってさばいていく仕組みだ。縫製場は複数人で稼働する小さな工場の場合もあれば、一軒家といった場合もある。
家庭内での縫製の場合、胴元が靴縫製に適したミシンを導入し、スキルを伝授して仕事として依頼するというものだ。以前はこうした経済循環が起こっていたが、今では不景気により受注数が減少。組織立った縫製工場はなくなり、一軒家など個人単位の縫製場が多い。しかしそれも高齢化にともない、問屋制家内工業の終焉は否定できない状態にまで来ているといっていいだろう。
過去にあったビジネスモデルから脱却し、新しい体系をつくり維持していくこと。工場側から見れば、先の「セトウチレザー」さんのような若い人達が新たに事業を起こし、これまでとは違う事業モデルでの縫製業というのもあるだろう。また、工場がブランドを立ち上げ、クラウドファンディングや自社EC、楽天やヤフーなどモールと呼ばれるプラットフォームを活用し、自らが直接エンドユーザーに向けて商品を販売する工場が増えている。
そして、僕たちの会社において縫製業に対してなにができるかと言えば、例えば「縫製とマーケティングができる」といったような複数のスキルを所持する人材をつくり、会社内で機能させること。製造業の賃金安のデメリットをカバーするような形で別の職能を併せ持つ形。
もう一つは自らが胴元となり、就労支援施設などに機械を導入し技術指導する、これまでとは異なる生産体系を作り上げるといったことが考えられる。どちらも簡単ではないのは承知している。正直ビジネスの効率としてみると、ミシンを使ったマシンメイドではなく、技術革新による生産方法を行うべきだと思う。ほめられた策だとは思っていないが、私自身にミシンによるステッチワークの魅力を感じ、伝え残していきたい技術的財産だと考えているので、その点はあきれ顔でも見届けていただきたい。
民藝に見た価値
さて国内生産の現状とこれからについて書いてきたが、つぎはブルーオーバーが影響を受けている民藝について話してみようと思う。民藝に関しての僕の考え方などや、それにどう影響されたのかというのはブルーオーバーサイトのアバウトや深堀コンテンツに記載しているので、そちらをみていただきたい。
さて、この二年、僕は改めて民藝に関して学んだのだが、別アプローチでも刺激を受けたものがある。株式会社cotenの配信する「コテンラジオ」という音声メディアだ。友人からの勧めで拝聴させていただいたのだが、このコンテンツにすっかりはまってしまった。コテンラジオは、これまで自分を形成してきた考え方を、離れたところから認識できるキッカケを与えてくれた。
コテンラジオはここ数年で話題になった人気のコンテンツで、歴史というとてつもなく長く深い内容を、民族、宗教、人物、出来事などに区切って紹介するコンテンツだ。解説の深井さんの語り口調がとても平易で聞きとりやすく、ゆるめの番組の空気感もあいまって、ついついはまってしまった。そしてある程度聞いていくと、長い歴史を俯瞰した視点で認識することができるようになった(これがめちゃ大事だったとおもう)。
ちょうどパズルを作っていくような感覚で一つ一つのピース(出来事)をはめ込んでいくと、やがて全体像(歴史)が見えていく感じに近い。それは歴史が常に相関しながら作られていくことの認識がより鮮明になり、これまで史実に対して断片的な理解によって生まれる偏見から解放してくれることが、このコンテンツの大きな魅力であると個人的には認識している。
そうした観点を学び、改めて自分のブランドの考え方を見直したとき、民藝という思想についてもこれまでとは異なる見方で整理をすることができた。僕の民藝に対する理解は若いうちは物質的な外観、道具が生まれる行為、背景によるものとして認識し、そこに文脈を見出すという、常に理由を求め理解する見方しかできなかった。それは柳宗悦氏がいう民藝の定義に対して、点でしか理解ができなかった自分がいたのだと今は思う。
だけど、宗教の歴史、仏教史を広く確認することで、これまでと違った民藝が僕の前に現れた。
僕の興味の対象は民藝でもあるが、一方で仏教も自分自身の生き方に大きく影響を与えている。だが、それらのつながりはお互いに点でしかなく、そこに線としての結びつきの自覚はなかった。だが、学びを重ねるうちに柳宗悦氏の仏教的側面からの民藝観というものが、うっすらではあるがわかったような気がした。それは氏の提言している無心の美に対する理解につながった(真意を突き止めるまではいかないけれど)。
無心の美
民藝の中に潜む仏教的観念を見出した柳氏の無心の美に関して、個人的解釈を述べたいと思う。
産地から生み出される民藝は、そこに働く人にとっての生活の一部であり、毎日同じものを繰り返し生み出し続けている。生み出しているその手は、やがて作り手の作為を離れ、無心の内にそのモノが生まれるという。その無心さは仏教でいう念仏と同義となり、ただ無心となることで救いを得るとう行為に通ずるのだと考える。無心から生まれでるものは救いであり、救いに美しさを見出したという理屈だ(ここで僕が仏教として『救い』を話すのは、まだまだ荷が重いのでこれくらいで勘弁してほしい)。
僕が民藝の魅力について改めて考えたとき、すべてのきっかけは柳宗理氏(柳宗悦氏のご子息)のハードウェアとしてのプロダクトデザインからであった。そこから僕は民藝を知ることになるのだが、その当時僕はデザイナーを職業としていた為、主として合理性(使い勝手や機能性といった言葉で説明がつくことを連想していただければ)からその魅力を紐解こうとしていたが、まったくの見当違いであった。
柳宗理氏の手掛けた製品には、手から生まれたぬくもり(愛着)が感じられ、合理性だけでは片付けられない奥深さ、美しさを体現しているが、当時の僕はそれを合理的に読み取ろうとした過ちを犯していた。それはまったくもって無知からくる行為であった。宗理氏は造形を生み出すアプローチとして手から生まれ出る造形を大事にしていた。繰り返し動かす手によって生まれ出る姿。そこに近代の工業化を重ねあわせていく。それはまさしく民藝のいうところの無心の美を、宗理氏自らの手によって試作を重ね続け生み出そうという壮大な試みだったのだろうと思える。情けないことに僕は今になってようやくその偉大さに気づくことになる。
さて、そうして仏教的側面からのアプローチによって今までの自分には見えていなかった民藝に気づくことになったのだが、これまで民藝の特性や美についての解釈において、無心の美だけが、うすらとわかったふりをしていた。しかし、仏教史を学ぶことで無心の美に対しての解像度が鮮明になったのは明らかだった。これは僕にとっては大きな気づきだった。そして実は自分が民藝に対して惹かれていた要素はこれまで、用としての側面。つまり機能性や、生み出される背景、その健全さだと理解していたが、実は「無心さ」にも大きく惹かれているのだということが、仏教を学ぶことによって明らかになった。
いずれにせよ、やはり民藝思想は僕にとって大きな影響を受けているのは間違いないらしい。だが、だからと言って民藝品を作ろうとしているのかと問われれば、それは違うとはっきりと言える。うまく説明できるかわからないが、民藝というのは僕は文化思想であり、社会から生まれ出るものだと考えるからだ。もし結果としてブルーオーバーが行っている活動が後々になって民藝だといわれるのであればそういうことになるのかもしれない。
アウトサイダーアートとよばれるもの
「無心」について説明するとき、また別のエピソードを話す必要がある。ある時、僕はヘンリー=ダーガーという人物を知った。彼の人生はとても興味深いもので、数十年をかけて彼は1万5000ページもの作品を残し、しかしこの作品は世に発表されることなく保管され、彼は生涯を終えることになる(世界的に有名な作家なので、彼のエピソードは検索すれば沢山知ることができる)。その膨大な量の作品を誰にも見せることなく、作り続けていたという事実。彼の人生は僕にとってあまりにも衝撃的だった。
僕はデザイナーとして働く時、クライアントから依頼された要求に対して、成果物を出し、対価として報酬を受け取る。依頼者がいて、目的のためにリサーチを行い、その答えは何かを考える。この関係はデザインを行う上でまったくもって当たり前の行為だと、疑うことはなかった。だが彼はそうではなかった。自分の描く世界を純粋に吐き出し続ける行為、それも尋常ではない量を日常の出来事として、だれに請われるでもなく作品を生み出し続けていた。僕には想像もできない行為だった。そしてそのアカデミズムに支配されていないクリエイティブは多くの人を魅了することになる。当然彼の生い立ちや背景をしった上での評価もあるだろうし、僕自身もその見方を含んでいるのは否定できない。そのうえで、彼の作品に衝撃を受けたといいたい。それだけ、純粋無垢のエネルギーは僕の心に衝撃を与えたものだった。そこで僕はアウトサイダーアートという言葉を知ることになる。
アウトサイダーアートは言葉の通り、アートと呼ばれる領域外(アウトサイド)にあるものと定義されている。例えば一般的美術教養を備えていない作品(アールブリュット)、民族における伝承されつづけてきた芸術品(フォークアート)。いわゆるファインアートに属していない作品に対して位置づけられると僕は認識している。
僕は日頃から、モノやコトにたいして、必ず人の意思が介在されているはずという認識があり、そして作為を無意識のうちに読み解こうとする癖があった。なにか理屈を見つけないと納得できないということだろう。おそらくデザイナーとして生きてきた職業病のようなものだと思う。そうした捉え方は、経済活動上で非常に有益に働くものだと理解しているし、悪いことではないと思っている。お互いがコミュニケーションをとりながら、相手の考えていることを読み取ることで、問題を解決することができるからだ。潤滑な関係性を築くために多くの人は意識的であれ、無意識であれ、意図をくみ取ることを行っているのだろう。
だが、そうした習慣が当たり前になるにつれて、昔は感じていた気持ちの揺さぶりといった経験が薄らぎ、回数も減っていった。それは社会活動においての、あたりまえやルールといった秩序に支配されることで得た、安心の結果なのかもしれない。お互いが効率的にストレスなく継続する為のやり方として、社会に適応するにつれて摩擦をさける行為。そういった風に僕はとらえている。しかしこうした行為は、却って見えていたものが見えなくなっているということにはならないだろうか。
経験値に基づく合理的判断が増えるにつれて、説明のつかないモノは思考から「排除」される。先の民藝の無心の美についても、社会的合理性から組み立てた場合、うまく説明のつかないモノとして判断され、真の理解にはたどり着くことができない。僕自身、そうした頭になっていた。だけど、説明のつきにくいものにこそ、経験と年齢を重ねることで薄まっていった心の揺さぶりの源泉があるのだと思うようになった。
ヘンリー=ダーガーのエピソードはそんな気づきのきっかけを作ってくれた。アウトサイダーアートは定義としてあまりにも広義だ。しかし僕は不思議なことにこのアウトサイダーアートと呼ばれるカテゴリーに属しているモノの多くに共感を覚える。そして、民藝もこの興味深いカテゴリーに該当していると考えている。そこには確実に僕がこころ揺さぶられるモノが存在している。それを一つ一つ説明することはできない。僕自身明確な答えをいまは持ち合わせていないからだ。だけど、明確な答えではないが、ぼやっとしたことなら言える。僕の心を揺さぶるそれは、人が生み出す合理性だけでは説明できない想像力(クリエイティビティ)だということ。そして無心へとつながっていること。これが民藝から出発して、これからたどり着くであろう、ブランドが掲げるビジョンへのヒントになるような気がしてならない。
アウトサイダーアートを知った僕は本当に驚いた。国内にも数多くのアウトサイダーアートに属する方々はいるが、私がより深く知るきっかけとなったのは、障がい者アートと呼ばれる世界だった(atelier incurve今中博之氏からするとこのカテゴリーづけにも異議があるといわれているが、経緯の説明上として使用)。ちなみに僕はアートの世界には深く精通していない。そもそもアートの文脈も知らず、興味も薄かったのが本音だ(今はすごい興味がある)。そんな素人がある日、会社のスタッフから見せられたのが平野喜靖氏の作品だった。まさに圧巻。これまでの、理屈を見つけ読み解こうとする僕の癖を阻むような、そんな氏の作品は、紐解くことすら一切許されなかった。氏の作品は文字が平面全体にびっしりと敷き詰められており、言葉としては意味をなさない。だがその敷き詰められた文字、言葉には彼独自の法則があり、それが一つのまとまりを見せている。そしてそれを生み出す平野氏は毎日、作品を吐き出すことをやめない。まさに無心でいつまでも繰り返す行為だ。僕の感情は揺さぶられ、ある種の救いすら感じた。これまで理屈で理解し、安心を固め続けてきた自分の価値観に大きく風穴を開けられた気分だった。そして障がい者アートに興味を抱いた、他のアーティスト作品を見ていくごとに、彼らのクリエイティビティに驚愕した。そして僕は自分の想像をいとも簡単に超えるモノが、こんなにも当たり前に展開されるのだということを知った。震えた。デザイナーである自分には絶対にたどり着くことのできない境地が彼らの世界には、いくらでも存在することを知った。
僕の中で諦めの感情が沸き上った。
メガネをかえる
僕は40歳を超える。自分でも初老だという認識はある。孔子は「四十にして惑わず」といったが、まだまだ自分というものが何かわかっていない。仲間内でミドルエイジクライシス(中年の感じる危機)だとか言い合った。自分の理想とする姿を描きながら追いかけ続けていた。「答えはきっとあるはずだ」と一生懸命に自分探しをしていた。だけど、そんな気持ちは追いかけて見つけようとすればするほど、霞んでいった。しかし、民藝の「無心の美」への理解から、アウトサイダーアート、障がい者アートを経て、自分の目指す到達点は自分自身には不可能だということを理解した。それは我欲がある限り行き着けない境地だと。へんな話だが、諦めという感情が生まれたことで、これまで追い求めようとした『欲』が取り除かれるような感覚になり、心が楽になった。
妙に大人になってしまい、ビジネスの世界を知ったかのような顔で、これが正解だといわんばかりに、さまざまな出来事をラベリングする行為をしていた僕は、いつしか退屈な目を持つようになったのかもしれない。博物学者の盛口満氏の著書「生き物の描き方」の中で「自然を観察するときのコツは『自然をみるためのメガネをかける』というふうにいい表せる。自然はいつもそこにあるが、普段は目に入らないものであるからだ。」と書かれていた。ここでのメガネは道具としての眼鏡ではなく、当人の視点、視座の話を指しているのだが、これはまさしく今の自分に当てはまる状況ではないか。ビジネスメガネを使用し続けたばっかりにその視座でしか物事を見れなくなっていたのだろう。だがメガネを変えることで全く違った世界が現れるということになる。これはビジネス競争から解放され、物事を異なる視座から見ると「四十にして惑わない」自分へのヒントがたくさんある考え方だった。
過去の自分にはその時の事実がある。当時どんなことを考えていたのか、いま思えば恥ずかしいことばかりだけど、その気持ちは本当だった。熱くなれた。若ければ若いほど、その理由は強く、理屈が通らないものばかりだ。
この気持ちは、大人になるにつれて失われていった。だが、これまでの学びを経て、今はこのエネルギーが大事なものだと思えるようになった。「ミュージシャンは一枚目のアルバムが一番いいよね。」というたとえ話を聞く。乱暴に言えば、その最初の一枚目が何物にも染まらぬ最も純粋無垢な気持ちを表しているからだろう。そこにオーディエンスは心打たれ、感動する。わかる気がする。もちろんそんなことは何の根拠もなく、アーティストは毎回全力を注ぎ作品を作っているのは間違いない。だけどファーストアルバムは当人にとっても思い出深いことは間違いないとは思う。それだけエネルギーが詰まっているということだろう。僕自身も人生はじめての経験というのは、いつもドキドキやワクワクを抱える。だから思い出深い記憶となるのは体感として理解できる。初めての試みこそ、ある種の「無心」が存在するのではないかというとらえ方だ。
心揺さぶられることが少なくなったといった僕は、自分自身でビジネスメガネを固定していたことにあるのだと気づく。同時に若さや、チャレンジといった機会で生まれるエネルギーが存在するのだということを見落としていた。ここで何が言いたいのかを整理すると、僕は同じメガネをかけ続け、いつの間にか偏った見方を続けていて、その結果退屈な目をもってしまったということ。そしてメガネを付け替えることで、これまで見落としていた大切なものに気づかせてもらったということ。それはこれからの自分自身の生き方のヒントとなった。
僕はあきらめにより、気持ちが軽くなったと言った。それは無心の境地でモノを生み出すという行為を、執心をもって行おうとしていたことからの解放ともいえる。伝えるのが難しいけれど、それは決して歩みを止めることではなく、無理をして自分を形つくることを止めることを意味する。その執着から削がれたことは僕にとって本当に気持ちが軽くなった。そして今自分が内をしたいのかをもっとメタ視点から考えることが出来るようになったのだと思いたい。
僕たちがやるべきこと
バトンという会社はモノを作る会社である。モノヅクリを通じて、僕たちは「生きる楽しさ」を伝えたいと思っている。すこしでもより良い社会になるように。僕たちの会社でその考えを最も表すブランドはブルーオーバーだ。だから、このブランドの歩む方向がこれからの会社としての指針にもなる。
これまでの僕は製靴産業の職人さんたちと歩んだ10年があり、その背景として民藝があった。そしてその未来には決して明るく輝くものは用意されていない。理想だけを語る年齢でもないし、この10年はその現実を知るためにあったと思っている。はじめにも書いたように日本という国に対して、これからはより厳しい現実になるのだろうという意見が多く聞こえてくる。モノヅクリ大国ニッポンといわれていたのは過去の栄光で、国内の多くを占める小規模の製造業は高齢化とともに後継者問題をはらみ、継続することが難しくなっている。
そんな状況で僕たちがやるべきことは、それでも国内生産を続けることだ。それはフランスの哲学者ベルクソンが唱える「ホモ・ファーベル」がまさに僕たちの活動の意味であると考えている。工作人を意味するホモ・ファーベルは、知性をもち、創造性を使い、道具生みだす行為こそが人類と定義される、というものだ。人が人である証明として、つなぎ続けてきた国内のモノヅクリを絶さないようにする。拡張することはないが、喪失しないようにすること。伝統産業のような歴史はないけれど、靴に携わるものとして作り続けた証明として、国内で靴をつくるという事実を保ち続けたいと思っている。そして国内生産を継続できる仕組みをつくる。大きな規模ではないけれど、失わないように持続可能な状態を作りあげること。これも僕たちがやるべきことだと考えている。
僕たちがやりたいこと
国内の製造業だけではなく、民藝から見出した「無心の美」の価値をモノに変換することがブランドの目指す姿とみている。その価値とは人が生み出すエネルギーあふれる想像力だ。この想像力こそがこれからの日本を支えるとても大事な「力」だと考えている。そしてそれを生み出せるのは、いま表現を行う、すべての人と定義したい。
自分がデザインする靴を買ってもらうことはとてもうれしい。だけど、人と繋がり合いながら成長していくブランドになることが今の僕の描くブルーオーバーの理想だ。 いまの時代だれもが表現者になれる。デジタルの恩恵は世界と繋がり合うことができ、伝えたいことや、表現を無限に受け入れるプラットフォームが存在するようになった。そしてだれしもが自由に参加でき、その考えを伝えられる。これまでになかったコミュニケーションの形がうまれている。旧来的なメディアだけに「伝える特権」を与えられていた時代は終わった。そして無限とも思える人の意思、主張が広がっていく。そしてそれは、言葉、絵、音楽、あらゆる文化芸術として姿を変えて目の前に映し出されている。そこには無限のエネルギーがマグマのようにたまっている。
そして、僕が障がい者アートに気づかされたように、無心に取り組む人の純粋な心から受けたインパクトをブルーオーバーを通して伝えたいと思っている。その主役はクリエイティブにかかわるすべての人だ。僕は我欲から解放されたとき、ブルーオーバーはもっとたくさんの人をもっとたくさんの人に届ける装置になりたいと願っている。
ハードウェア(物質的な道具)を作ることが出来る僕らは、僕たちが素敵だと思う創作活動のクリエイティブを受け止め、スニーカーへと変換する。それがブルーオーバーを通じて多くの人に出会うきっかけになること。そこにみんなが刺激を受け、元気になってもらうこと。もちろん、届ける僕らや、一緒につくったクリエイター、アーティストもうれしい。それがつながりあいながら拡張していく状態。デジタル上では当たり前に繰り広げられていることだけど、リアル世界ではまだまだ行われていない。平易だけど、そういうこと。これが僕たちがこれから先にやっていきたいことだ。
日本の可能性
僕は日本という国は改めて特殊だと感じている。西欧(白人)中心の歴史や宗教観を辿らず、近代化に成功した日本は国力を増していった。やがて第二次世界大戦を経て、敗戦国となりアメリカによって民主化が進んだ。その後、みごとな経済成長を遂げ大きな発展をとげたのだが、グローバル化となった現代社会では遅れをとっていると言われている。
日本がうまく時代の波に乗れていた時は、社会全体の成長のベクトルと日本の特性(加えて、人口も増加していた)がうまくかみ合っていた為、大きく成長していくことができたが、テクノロジーの進化に伴いその手段が変わった為、流れに乗れなくなってしまった。流れに乗り切れていないまま、社会は次の時代へと変容していく、それは国家という境界線がありながらも、個人がボーダレスにつながりあえるというこれまでにない社会が訪れている。それはこれからを生きていくとき、自分たちの国の文化だけを理解するのではなく、誰もがお互いを理解していく必要があるということだ。
ここで僕はこれからの時代こそ、文化人類学(民族学)という学問が重要であると考えている。構造主義の祖として知られるレヴィ=ストロースが概念として「熱い社会」「冷たい社会」という言葉を使ったが、この未開人の社会構造を指した「冷たい社会」というものに、僕は持続可能な社会(SDGs的な?)のヒントがあるのではないかと考えている。競争や戦争といった形で文化、文明を進化させていくことは、人の生活を豊かにするのだろうとは思う。僕らもその恩恵の上で生活をしている(ちなみにこれを「熱い社会」と定義している)のは紛れもない事実だ。だけど、この進化は、自然環境に対しても人類に対してもストレスをもたらしつづける。その構造はすでに限界点に来ているのではないだろうか。これからはドラスティックな変化ではなく、自分たちの民族(環境)を維持し続けるための、循環型の変化が必要だと考える。
「冷たい社会」として定義づけられた、未開人が作りあげる社会構造は、レヴィ=ストロースが愛した日本文化にも見出せるのではないか、そしてそれはこれから変化していく社会の方向性に順応するのではないか。その日本文化とは柳宗悦の「民藝思想」や、谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」などにみられる価値がそれだ。西欧近代の自然を破壊し、新しいものに構築する手法ではなく、自然を破壊しながらも共生する方法を日本人は巧みに見出せる民族だということ。それは近代化以前にあった日本人の風習、信仰に見て取れる。元来日本人にはそうした理性を宿しているのではないか。そしてその価値観こそがこれからの社会に必要とされるあり方だと思っている。
自然と共生し、膨張することなく、無理なく継続できる規模で社会を循環させる。これからの社会がそうなってほしいと願いのだが、僕らのブランド、会社はそうあるようにしていこうと考えている。そして僕たちの会社がモノヅクリであることは人が人である証明を行うことであり、そこに人の意思、創造性がふんだんに取り入れられること。AIの活動領域ではなく、人でしかできないことを活かせるブランドとして、これからの日本人の莫大なエネルギーを活かせる会社としてがんばりたい。
おわりに
思ってた以上に長くなってしまいました。言葉の選定に自信もなく、文章もまだまだ迷いがあるものだとは思っていますが、あまり整え過ぎず書き終えることにしました。この冊子を手に取りここまで読み終えた方は、おそらくブルーオーバーに興味を持っていただいたお客様だと思います。本当にありがたい気持ちでいっぱいです。 これから僕たちが行っていく活動を、是非ともあたたかな目で見守りながら、応援いただければすごくうれしいです。そしてブルーオーバーを知っていただくこと(履いていただくこと)で、ご自身の時間がとても満足できることのなるように、ブルーオーバーは精一杯頑張ります。